こんにちは、れい(@reilifedesign)です。
「長期的に考えよう」
「将来を見据えて判断しよう」
——よく耳にする言葉ですが、日々の忙しさの中で
「そんな余裕ないよ」
「目の前のことで精一杯」
と思ってしまうこと、ありませんか?
そう考えているであろう人を見ると、
「んー、大丈夫かな…。ちょっと心配だ。」
と感じます。
実際、大学で学生を見ていても「長期的な視点を持つこと」が難しいと感じている人が多くいます。
けれど、私たち研究者の世界では「長期的な視点」がなければ、何ひとつ形になりません。
むしろ、数年、時には十年以上のスパンで物事を見て、試行錯誤を繰り返しています。
それは研究だけに限らず、「暮らし・勉強・仕事・人間関係」すべてにおいて共通する考え方です。
- 長期的な視点と短期的な視点の違い
- 判断力を高める「視点の切り替え方」
- 人間関係・教育・自己成長への応用例
- 忙しくて目の前のことで精一杯な人
- 判断に自信がない人
- 将来が漠然と不安な学生や若手社会人
「考えの設計」って何?という方へ。考え方はより良くできます。
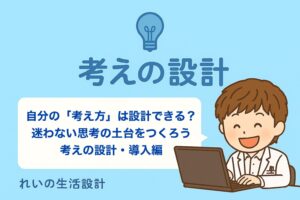
長期的な視点とは?

まず、「長期的な視点」とは何を指すのでしょうか。
簡単に言えば、
「今この瞬間」だけでなく、未来の自分や周囲の変化を見据えて判断する視点のことです。
たとえば就職活動。
「今この会社に入れば楽そう」とだけで選ぶのか、
「将来やりたいことに近づける会社はどこか?」と考えるのかで、
その後の人生の満足度は大きく変わってきます。
 れい
れい大学でも、インターンを面倒がって後回しにしていた学生が、就活本番で『もっと早く動いておけばよかった』と後悔している姿を何度も見てきました。
これは学生だけではなく、社会人でも同じです。
キャリア、人間関係、健康、お金——
どんな場面でも、「今の選択が未来にどう影響するか」という視点は欠かせません。
なぜ長期的な視点が必要なのか?


では、なぜその「長期的な視点」が重要なのでしょうか?
それは、行動の“質”を上げるためです。
目の前のことに必死になるだけでは、
「その場しのぎ」になりがちで、いつまで経っても同じ課題に追われてしまいます。



実際、私自身も研究で経験があります。論文を書くことに必死になりすぎて、途中で『あれ、そもそも何のためにこの研究を始めたんだっけ?』と目的を見失ったことが何度もありました。
研究は、数年単位で成果が出る世界。
目先のタスクばかりに目を向けると、本質が見えなくなってしまうのです。
けれど、
「この研究が5年後にどう役立つか」
「今の積み重ねが、後輩や社会にどう還元されるか」
といった長期的な意義を見つめ直すと、
「今やっていること」にも自然と意味が生まれ、モチベーションが湧いてきます。
長期的な視点は、「意味」と「やりがい」をつくる


忙しいとき、目の前の作業に追われて「意味がわからない」と感じることがありますよね。
そんなときこそ、長期的な視点が助けになります。
- なぜこの作業が必要なのか?
- これを続けた先にどんな未来が待っているのか?
- 誰に喜ばれるのか?自分はどう成長できるのか?



意味が見えると、人は「頑張れる」。
これは学生も、大人も、研究者も同じです。
物事を判断するときには、長期的な視点と短期的な視点の両方が存在します。
次に、それぞれの違いを見ていきましょう。
長期的な視点と短期的な視点の違いとは?


私たちが何かを判断するときには、「短期的な視点」と「長期的な視点」の2つがあります。
短期的な視点: 目の前の課題や目先の結果にフォーカス
長期的な視点: 将来を見据えた、余裕や成長を生む判断軸



短期的な視点は大事。
でも、それだけじゃ「前進」はできないんだよね。
私自身も、研究を進める中で目の前のタスクに追われて迷子になることがあります。
でもそのたびに、
「そもそも何のためにこれをしていたんだっけ?」
と立ち返る時間を作っています。
判断力を高めるには「視点の切り替え」が必要





視点が固定されていると、判断も行動も偏ってしまうんです。
人生の選択に正解はありません。
だからこそ必要なのは、“今”と“未来”の両方を行き来しながら考える力、つまり「視点の切り替え力」です。
具体的には、こんな考え方ができるようになることです
- 「今は忙しいけれど、この手間が後々ラクになるかどうか?」
- 「今日の判断は、未来の自分を助けるものか?」
- 「今は効率が悪くても、長い目で見ればチームが育つのでは?」
逆に、短期的視点に偏っていると…
- とにかく今の仕事を片付ける
- 今の自分が楽になる選択を優先する
- 面倒なことは避ける
このような思考が当たり前になり、「その場はうまくいっても、同じ問題が何度も起きる」ことにつながります。
れい
「一時的な“ラク”が、長期的には“ツケ”になることもあるんです。」
視点を切り替える習慣があると、冷静な判断ができるようになります。
これは勉強や仕事だけでなく、人間関係やお金の使い方など、あらゆる場面で活きてきます。
事例:上司の視点が変わると、未来も変わる


ここでは、「短期的な視点で判断する上司」と「長期的な視点で判断する上司」の違いを通して、視点の影響力を具体的に見てみましょう。
同じ「忙しい」という状況でも、視点の違いで結果がまったく変わります。
短期的な視点の上司
- 「部下のことは知らない、自分で考えて動いてほしい」
- 「自分がやった方が早い」
- 「今忙しいから、それどころじゃない」
一見、効率的で合理的に見えるかもしれませんが……
- 部下はいつまで経っても成長しない
- 質問しづらい空気がチームに広がる
- 上司本人がいつまでも抱える仕事が減らず、慢性的に忙しい状態が続く短期的な視点の上司
長期的な視点の上司
- 「部下が迷わないように質問しやすい空気を作ろう」
- 「最初は手がかかっても、後で助けてもらえる」
- 「チームで協力し合えた方が、みんなが気持ちよく働ける」
結果として…
- 部下が自信を持って行動できるようになる
- 少しずつ業務を任せられるようになり、上司にも余裕が生まれる
- チームの雰囲気も良くなり、成果が出るスピードも上がる
みなさんは、どちらの上司のもとで働きたいですか?



短期的には非効率でも、長期的には“人が育つ環境”が、結局いちばん効率が良くなるんです。
これは教育現場でも全く同じです。
学生に手間をかけて丁寧に指導することで、4年後には自分で考えて動ける人材へと育っていきます。
短期的な視点では「今だけ」しか見えません。
でも、長期的な視点を持てば、「人を信じて育てる」という選択肢が生まれます。
長期的視点だけでもダメ。大事なのは「バランス」
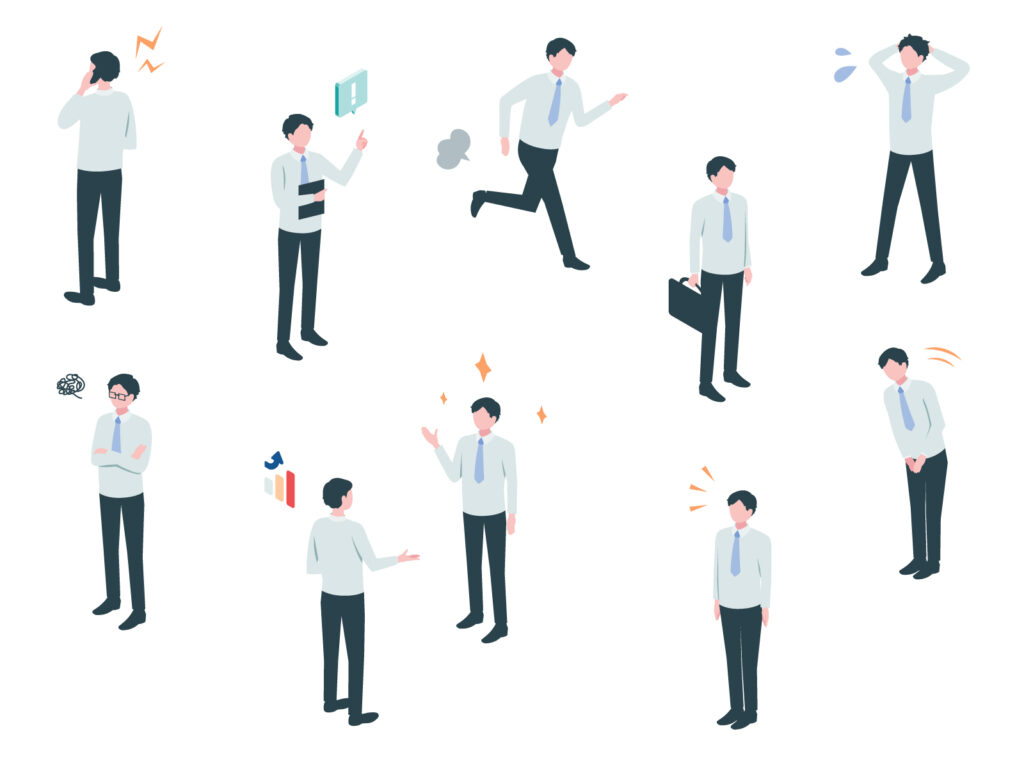
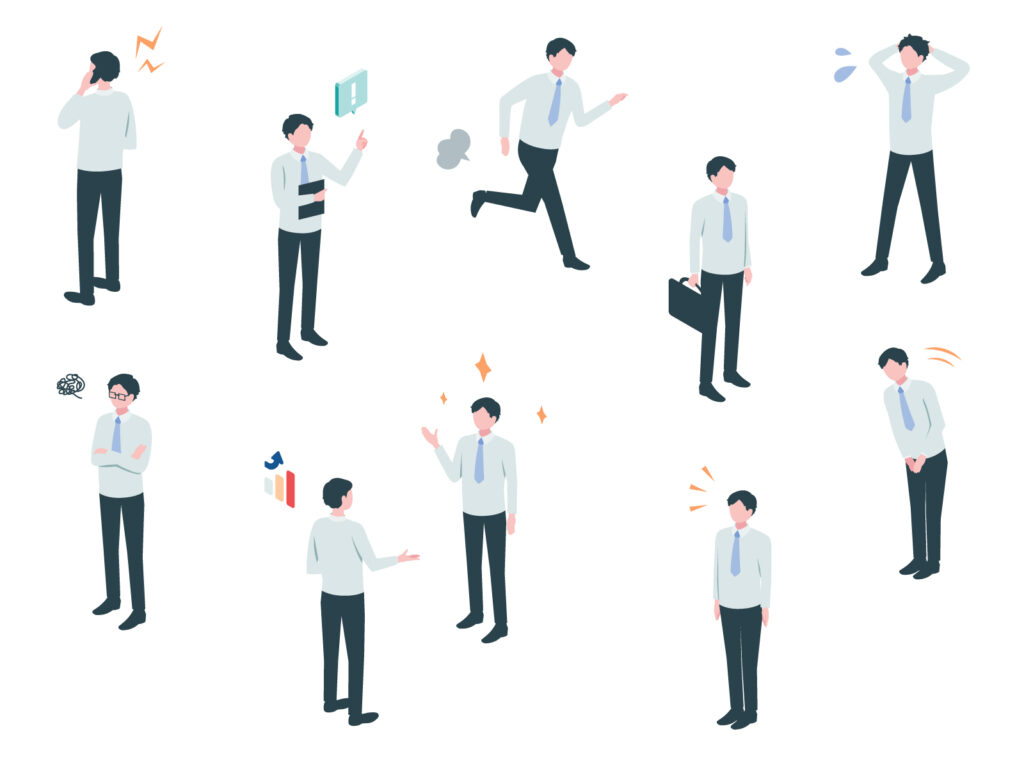
「長期的な視点」が大切とはいえ、目の前の課題から逃げているだけでは何も進みません。
大切なのは——
短期的視点で「今」を処理しつつ、長期的視点で「未来」を設計すること。



「目の前だけ」でも、「先のことだけ」でもバランスを欠くと前に進めない。
例えば、こんな時間を活用してみてください
- 電車の中
- 歯を磨いている間
- 昼休みの10分間
「この先どうなりたいか」
「今していることは、そこにどう繋がるか」
そんな問いを自分に投げかけてみるだけでも、視点が変わります。
まとめ|長期的視点は、未来への“投資”


今回は、「長期的な視点を持つことの大切さ」についてお伝えしました。
✅ この記事でお話ししたこと
- 長期的な視点とは?
→ 未来の自分や周囲の変化を見据えて、今の判断をする視点 - なぜ長期的な視点が必要なのか?
→ 行動の意味ややりがいを生み出し、継続や成長につながるから - 短期的な視点との違いと役割
→ 短期=今に対応する力、長期=未来を設計する力 - 判断に迷うときは、両方の視点を持ってバランスをとることが大切
- 実践のヒント:1日5分、未来を考える時間を作ることから始めよう



短期的な視点で「今」に集中しながら、長期的な視点で「未来」を見据える。
この組み合わせこそが、人生の選択にブレない軸をつくります。
「短期的に考えたら面倒でも、長期的に見ればきっと意味がある」
そう思えたとき、あなたの行動は大きく変わります。
「今すぐ成果は出ない」
でも、だからこそ——未来を変えるのは今のあなたです。
「みんなで笑顔になる暮らし」の第一歩を踏み出してみませんか?










