なぜだかやる気が続かない。やりたいはずの勉強や仕事が、思ったほど前に進まない。
そんな日って、誰にでもありますよね。
 れい
れいわかります!私も「今日は空回りばっかりだなぁ…」って感じる日、結構あります。
こんにちは、れい(@reilifedesign)です。
大学教員・医療系研究者として、日々「原因(なぜ起きたか)と結果(どうなったか)」を確かめる仕事をしています。



物事には必ず「因果関係」がある。だから、前に進めないときも必ず「手がかり」は見つかるはず!
そんな研究者が、因果関係の使い方と因果関係の捉え方を、日常で試せるレベルまで噛み砕いて解説します。
勉強・就活・仕事・人間関係…どの場面でも応用できる「前進のコツ」を、一緒に身につけましょう。
- 因果関係とは何か(超シンプル解説と具体例)
- つまずきを解く「因果関係の使い方」ステップ
- 未来に効く「良い捉え方」と避けたい「悪い捉え方」
- 勉強・仕事のやる気が続かず、原因を言語化したい人
- つまずきの理由を見つけ、効率よく前進したい人
- 思考のクセを整え、将来の選択肢を広げたい人
「考えの設計」って何?という方へ。考え方はより良くできます!
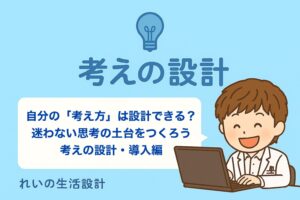
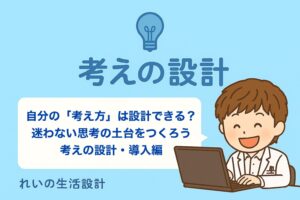
そもそも因果関係とは?
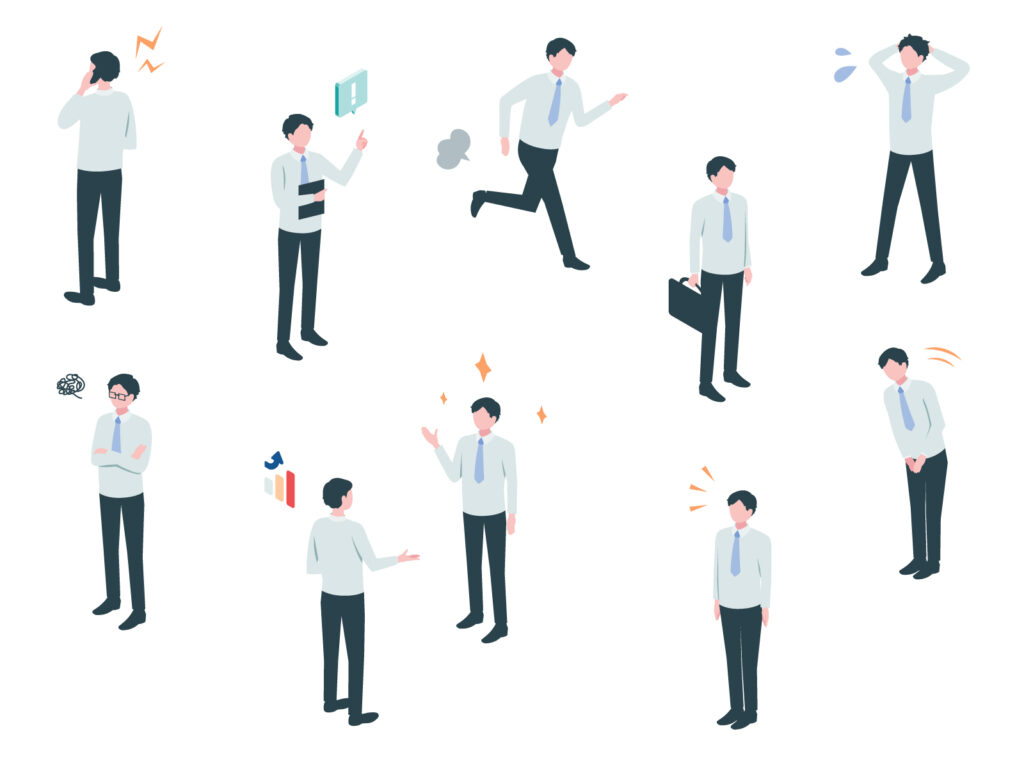
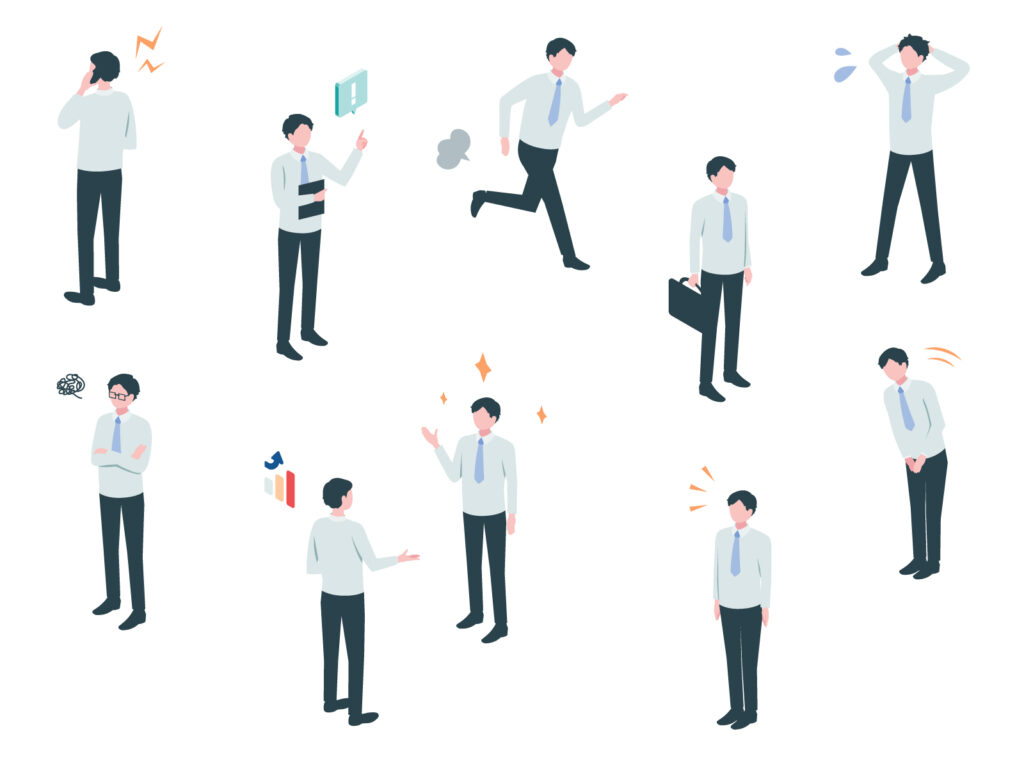
「因果関係」ってよく耳にするけれど、はっきりイメージできていますか?
例えば、
- テスト勉強を効率よく頑張ったから(原因) → 高い点数が取れた(結果)
- 夜ふかしをしたから(原因) → 朝なかなか起きられなかった(結果)
こうした「原因と結果のつながり」こそが因果関係です。
辞書的に言うと、因果関係とは「原因と、それによって生じる結果との関連」のこと。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「なぜそうなったか」というシンプルな話なんです。



日本語の文章で説明すると難しく感じるけど、生活の中ではみんな無意識に使ってますよね!
因果関係を意識するメリット
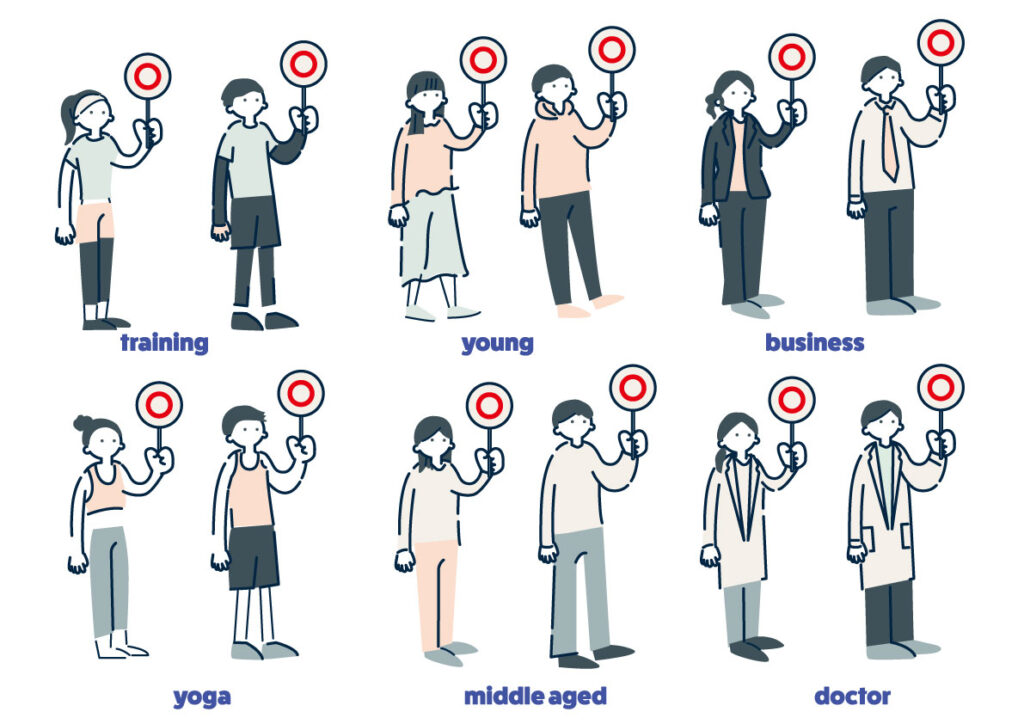
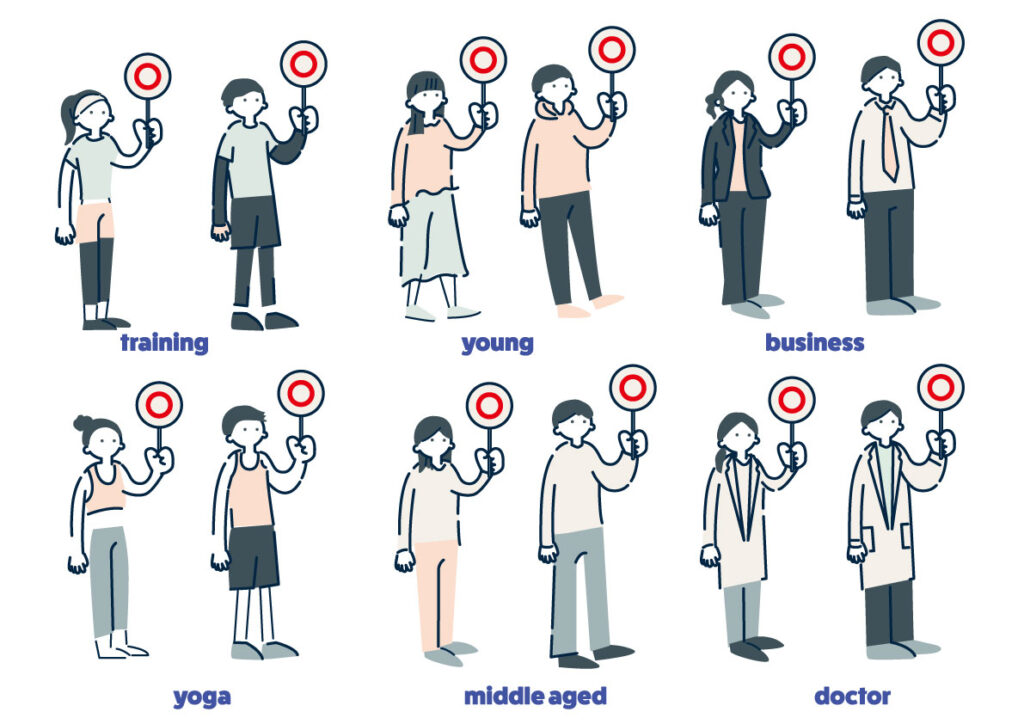
では、因果関係を理解したうえで「意識する」と、どんな良いことがあるのでしょうか?
ここを押さえておくと、日常の考え方や行動に大きな変化が生まれます。
1. 悩みや不安を整理できる
「なんとなく不安…」「やる気が出ない…」といった漠然とした気持ちは、原因を特定するまで頭の中でぐるぐる回り続けます。
しかし「なぜ不安なのか?」を因果関係で考えると、悩みが具体化されます。
たとえば、
- 勉強がはかどらない → 眠気や疲労が原因かもしれない
- 資格勉強に集中できない → 本当に必要かどうか目的が曖昧なのかもしれない
原因を言葉にできると、「じゃあどうする?」と一歩踏み出しやすくなります。
2. 効率よく行動できるようになる
原因と結果の関係を意識すると、「行動の優先順位」を整理できます。
同じ努力をするにしても、手当たり次第に動くのではなく「最も影響の大きい原因」から対処した方が効果的です。
たとえば、
- 夜ふかし → 翌日眠くて集中できない
→ まずは就寝時間を整えることが一番の改善策 - タスクが多すぎて不安 → どれから手をつければいいか混乱する
→ リスト化して優先度をつければ、心の負担が減る
このように「結果を変えたいなら、まず原因に手を打つ」という発想が行動をシンプルにしてくれます。
3. 成長につながる習慣が身につく
原因を探して改善する習慣を続けていると、自然と「小さなPDCAサイクル」を回せるようになります。
「原因を考える → 行動する → 結果を見る → さらに原因を探す」という流れは、勉強や仕事だけでなく、人間関係や生活習慣の改善にも役立ちます。
積み重ねるほど「考え方の筋トレ」になり、自分の強みや弱みを客観的に把握できるようになります。



やみくもに頑張るより、原因を見つけて対処した方が、実はラクだし成果も出やすいんです!
因果関係の使い方を身近な例で学ぶ


因果関係を意識するメリットがわかっても、「実際どう使えばいいの?」と思うかもしれません。
ここでは、日常のよくある場面を例に、因果関係の使い方を紹介します。
因果関係の使い方①:やる気が出ないときの原因を探す
資格の勉強を始めたのに、なぜかやる気が出ない…。
そんなときは、まず「原因」を探すところからスタートします。
- もしかしてお腹が空いている? → ご飯を食べる
- 疲れている? → 少し仮眠を取る
- それでも改善しない? → そもそもその資格が自分に必要なのか見直してみる
れい
「私は実際に“この資格、別に要らないな”と気づいて途中でやめたことが2回あります(笑)」
一見「時間をムダにした」と思うかもしれませんが、原因を探った結果「自分にとって不要」と判断できたのも大きな収穫です。
因果関係の使い方②:タスクが多すぎて不安なときの整理法
「やることが多すぎて、不安で押しつぶされそう!」
そんなときも因果関係を活用できます。



私は、タスク処理に対して一番因果関係の考え方を使っている気がします!
- 原因探し:不安の原因は「やるべきことが頭の中で混ざっているから」
- アプローチ:タスクをリスト化して一つずつ可視化
- 結果:不安が整理されて「やれば終わる」と安心できる



この方法をやるようになってから、不安で眠れなくなることがなくなりました!
もちろんすべてがスムーズにいくわけではありません。
それでも「原因を探す→対処する→結果を振り返る」という流れを繰り返すことで、前進できるのです。
因果関係の捉え方には種類がある


ここまで「因果関係を意識すれば前進できる」とお伝えしてきました。
ただし注意点があります。
それは、因果関係の捉え方にも「良いパターン」と「悪いパターン」があるということです。
良い捉え方=未来に目を向ける
「未来をどう変えたいか」に視点を置くと、因果関係は成長のための武器になります。
- 過去に努力したから(原因) → 今の自分は少し成長している(結果)
- 今の行動を工夫するから(原因) → 将来もっと成長した自分になれる(結果)
未来を起点に因果関係を考えると、
- 今できないことができるようになる
- 同じ作業でも効率化して余裕ができる
- やるべきことの精度を上げられる
といった「選択肢が広がるポジティブな連鎖」をつくれます。
ただし、ここでもう一つ大切なことがあります。
今の行動を変えたからといって、必ず未来が良くなるわけではありません。
あくまで「良くなる可能性が高まる」ということです。
何もしなければ、その可能性すら上がらない。だからこそ、行動して試し、検証し続けることが必要です。
仮説検証考察が大切な理由を解説しています!小さな仮説と検証の繰り返しが、未来をより良くする確率を高めてくれます。





未来に目を向けると、因果関係は「自分をアップデートするための地図」になります!
悪い捉え方=過去に縛られる
逆に「過去」にとらわれすぎる因果関係は、自分を動けなくしてしまいます。
- 今うまくいかないのは、あの失敗のせいだ(原因) → だから結果も変わらない
- 何をしても成果が出ないのは、私に能力がないからだ(原因) → だから挑戦できない
このように過去に視点を固定すると、行動の選択肢はどんどん狭まります。
「現状維持のための言い訳」として因果関係を使ってしまうと、成長の芽は摘まれてしまうのです。
ただし、ここで誤解しないでほしいのは、過去に失敗した人が必ずその後も失敗し続けるわけではないということ。
誰にでも失敗の経験はありますが、それを「学びの材料」として未来に活かせる人もたくさんいます。



後ろ向きな因果関係の捉え方は、選択肢を狭めるばかり。百害あって一利なし!
まとめ|因果関係を味方にして前進しよう


今回の記事では、因果関係の基本から使い方、そして良い捉え方と悪い捉え方について紹介しました。
本記事のポイントは以下のとおりです!
- 因果関係とは?
原因と結果のつながりのこと。身近な行動や習慣にも当てはまる。 - 因果関係を意識するメリット
悩みや不安を整理できる。効率よく行動できる。習慣化すれば成長につながる。 - 因果関係の使い方
「原因を探す → 対処する → 結果を振り返る」を繰り返す。
やる気が出ないときやタスクが多すぎるときも応用可能。 - 因果関係の捉え方の違い
良い捉え方=未来に目を向けることで、成長の可能性が高まる。
悪い捉え方=過去に縛られることで、選択肢を狭めてしまう。
行動を起点に未来をデザインしていくと、少しずつでも前に進むことができます。
失敗してもやり直せるし、試行錯誤することで「より良い未来」の可能性は確実に高まります。



自分自身はいくらでも変えられます!行動を原因にして、未来の結果をより良いものにしていきましょう!
考え方を改善し、行動を積み重ねることで、自分も周囲も笑顔になれる環境を整えていけます。
さあ、みんなで「笑顔になる暮らし」の第一歩を踏み出してみませんか?










