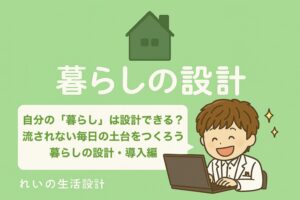「気づいたら今月もギリギリだった…」
「どうしてお金が貯まらないんだろう」
そんなふうに感じたことはありませんか?
学生生活でも、社会人になってからも、
お金との付き合い方は、じつは私たちの暮らしや心に深く影響しています。
にもかかわらず、学校ではお金の使い方や守り方をしっかり学ぶ機会は少なく、
なんとなく使って、なんとなく足りなくなってしまう。
そんな人も多いのではないでしょうか。
でも、お金に強くなることは、特別なスキルがいるわけではありません。
ほんの少しの「見える化」と「仕組みづくり」で、
ムダに流されない、自分らしいお金の使い方はきっと実現できます。
- 「お金を設計する」とはどういうことかがわかります
- お金の不安を減らすための視点が見つかります
- 無理なく管理できる仕組みづくりのヒントが得られます
- お金がなかなか貯まらないと感じている
- 家計簿や節約が長続きしない
- 自由に使えるお金が欲しいけど、不安で踏み出せない
お金は「感情」で動いてしまうもの

たとえば、疲れた日にコンビニでつい買ってしまう甘いスイーツ。
友達との誘いに断れず何度も外食してしまう週末。
買うつもりのなかった洋服を、「セールだから」と手に取ってしまうネットショッピング。
こうしたお金の使い方に共通しているのは、
「なんとなく」や「気分」で動いてしまっているということです。
お金は、気持ちと深く結びついています。
だからこそ、「気づいたらお金がない…」という状態になりやすいのです。
でも、逆に言えば、
お金の使い方に“仕組み”や“意図”をもたせることで、
流されにくくなるのも事実です。
お金の設計ってどういうこと?

「お金の設計」とは、
自分にとって大切なことに、必要なお金を使える状態をつくることです。
設計と聞くと、堅苦しく感じるかもしれませんが、
実際はとてもシンプル。
何にお金を使いたいのか?
どこで無駄が出ているのか?
将来に向けて、どんな備えが必要なのか?
このような問いに、少しずつ自分なりの答えを持ち始めることが、
お金の設計の第一歩です。
「ムダに流されない仕組み」をつくる3つの視点

お金をどこにどれだけ使うかは、人によって大きく異なります。
自分自身の満足度を高く生活するためには、しっかりと管理をしてお金を使っていく必要があります。
 れい
れいいくら使っても良いのかを把握できると、気兼ねなくお金を使えるからストレスもありません!
1. お金の流れを「見える化」する
まずは、自分がどこにお金を使っているかを把握することが大切です。
家計簿アプリやスマホのメモなど、続けやすい形でOK。
使った金額よりも、「何に」「どんな気持ちで」使ったかを振り返ることがポイントです。
数字だけでなく、「使ってよかった」「後悔した」といった感情も記録してみると、
あなたの「価値観」に合った使い方が少しずつ見えてきます。
2. “自動化”できる部分は仕組みに任せる
毎月の貯金を「余ったらする」ではなく、「先に分けてしまう」。
光熱費や通信費を「見直さなきゃ」と思いながら先送りにせず、定期的に見直す習慣を入れる。
こうした仕組みをつくることで、意志に頼らず続けやすくなります。
たとえば、「給料が入ったらすぐ貯金口座に1万円移す」など、ルールを先につくることが有効です。
3. 自分にとっての「豊かさ」を定義する
無駄遣いとは、本当にお金を使ったことそのものではありません。
「本当は要らなかったもの」に使ったときに、はじめて“ムダ”になります。
逆に、気持ちが整うカフェ代、大切な人との時間、知識や経験に投資することは、
たとえ高くても“豊かな使い方”と言えるかもしれません。
だからこそ大切なのは、自分にとっての豊かさとは何かを知ること。
それを見失わなければ、お金の使い方はもっと心地よくなるはずです。
「れいの生活設計」で伝えたいこと


この「お金の設計」では、
・お金に対する不安を減らしたい人
・自分なりのルールを持って自由に暮らしたい人
・無理な節約ではなく、納得してお金を使いたい人
そんな方へ向けて、
**“お金に流されず、自分の意思でコントロールする力”**を育てるヒントを発信していきます。
難しい専門知識ではなく、
日々のちょっとした気づきや工夫から始められることを大切にしていきたいと思っています。
✨ まとめ:お金の使い方は、人生の方向性とつながっている


- お金に振り回されるのではなく、自分の暮らしに合わせて使っていく。
- そのために必要なのは、「管理」ではなく、「設計」という視点。
- 完璧じゃなくていい。小さな見直しや仕組みづくりから始めよう。
「みんなで笑顔になる暮らし」の第一歩は、
自分のお金とちゃんと向き合うところから、始まるかもしれません。