こんにちは、れい(@reilifedesign)です。
大学生活って、自由ですよね。
大学や学部にもよりますが、出席回数をクリアしていれば授業に出るも出ないも自分次第、生活リズムも自分次第。
でも最近、その「自由」がちょっと違う方向に進んでしまっている学生を見かけることが増えました。
 れい
れい“怒られない=問題ない”と思っている学生が本当に増えました。誰にも迷惑かけてないしって、堂々と言うんです。
もちろん、大学は小中高と違って管理されすぎる場ではありません。
でも、それは「社会に出る準備の場」だから。
自分で考え、自分で動ける人に育ってほしいからこそ、あえて自由が与えられているんです。
にもかかわらず、提出物は雑、メールは失礼、教室は散らかしっぱなし。
このまま社会に出たら…と、心配になってしまう場面が少なくありません。
- なぜ大学生活が「自由」だけで終わってはいけないのか
- 社会に出られない学生の共通点
- 今すぐ見直したい、基本の習慣5つ
- 自分の大学生活、このままでいいのか不安な人
- 社会に出たときに信頼される人になりたい人
- 教員や先輩からのアドバイスにピンとこない人
「考えの設計」って何?という方へ。考え方はより良くできます。
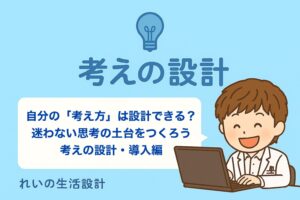
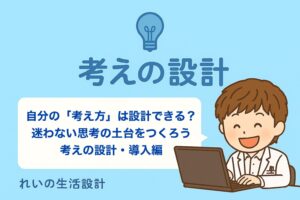
小さな行動が信頼を失う原因に。日常の「なんとなく」に潜む危険を解説しています。


大学生活は「自由」だけじゃない
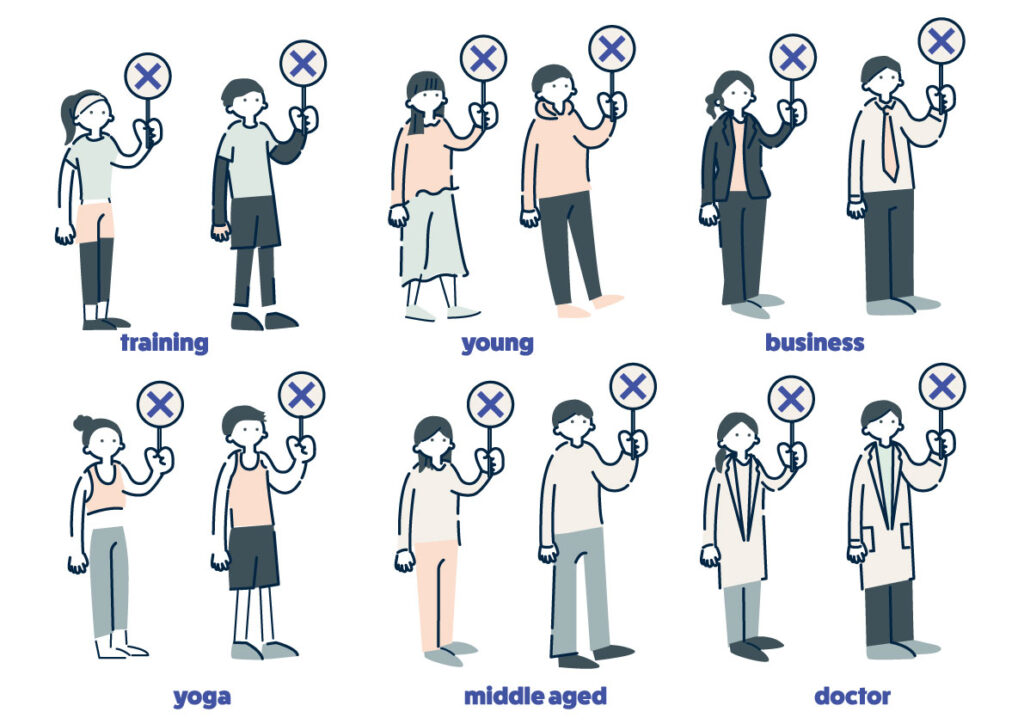
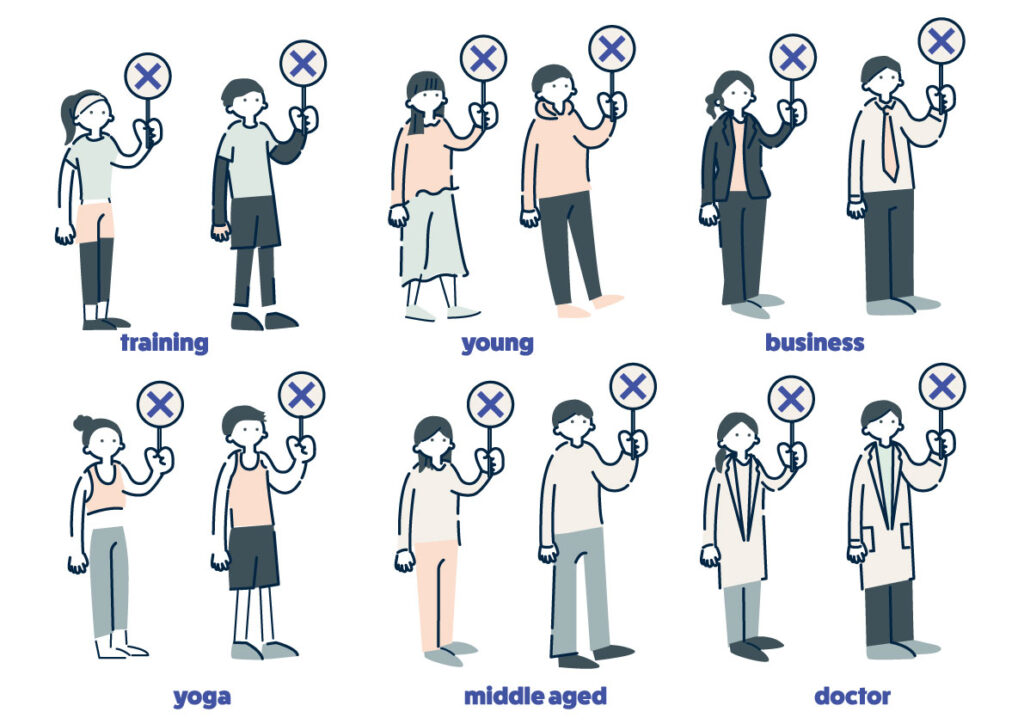
大学に入ると、一気に自由度が増します。
大学や学部にもよりますが出席の管理もゆるやかになり、時間の使い方も人間関係も自分の裁量次第。
けれど、その自由は「社会に出るための訓練」の一環であることを忘れてはいけません。
自由の中にある“社会の縮図”
大学生活には、社会の予行練習のような要素がたくさんあります。
- 期限を守る(提出物)
- 敬意を払って連絡する(メール)
- 整理整頓(職場環境)
- 時間を守る(遅刻・連絡)
- 多様な人と関わる(組織・上下関係)



自由って、好き勝手に生きていいって意味じゃないんですよね。本当は“責任を持つ力を育てる”ってことなんです。
社会に出られない学生の共通点


私が教員として日々学生と接している中で、将来が少し心配になる学生には、いくつかの共通点があります。
これは学力や能力の話ではありません。“態度”や“姿勢”が原因で、信頼を失ってしまうケースが多いのです。
共通点① 提出物が雑・締切を守らない
「出せばいいでしょ」という気持ちが透けて見えるような提出物。
・誤字脱字
・名前なし
・ファイル名が「無題.docx」
など、受け取った側は「この人、丁寧に扱ってくれてないな」と感じてしまいます。
締切も「誰も怒らないし、あとでいいでしょ」と勝手に判断して遅れて提出。
社会ではこのような振る舞いは
「だらしない」
「信用できない」
と受け止められます。
日々の小さな行動が、マイナスな印象を作り上げてしまうのです。



社会に出たら、“提出物=仕事そのもの”です。雑な資料は、あなたの評価を一瞬で下げます。
共通点② メールが書けない・返信がない
メールに件名がない。
本文に
「お世話になっております」
「よろしくお願いいたします」
などの基本的な挨拶もない。
こうしたメールは、教員であっても読みながら戸惑います。
社会では、こういったメールは基本的に“非常識”と判断され、返事すらもらえないこともあります。
もっとひどいと、そもそもメールの返信が来ないということも。



自分が送ったメールには、早く返信が欲しいと思っているのにね…。
企業とのやりとりでは、そんな対応ひとつで内定を逃すこともあります。
返信が遅い・返さないといった行為は、信頼を損ねます。
「この人とは一緒に仕事したくない」と思われる原因になるのです。



文章で相手に敬意を伝えること。これができる人は、就活でも面接前から“できる人”だと思ってもらえます。
共通点③ 整理整頓ができない
整理整頓は、「自分を整える力」の基本です。
・机の上が散らかっている
・リュックの中がぐちゃぐちゃ
・プリントを何週間もカバンに入れっぱなし。
こうした状態は、ただの“だらしなさ”ではなく、自己管理の弱さや優先順位の甘さとして見なされます。
そんな状態では、仕事も人間関係もうまくいきません。
整理整頓ができない人は、必要な情報をすぐに取り出せなかったり、準備不足で授業や仕事に臨んだりする傾向があります。



整った環境は、集中力も思考力も引き出します。逆に散らかっていると、何もかもが中途半端になります。
共通点④ 態度が幼い・相手によって変わる
社会に出たときに、その“差”は思っている以上に見抜かれます。
授業中にあくび、スマホ、ノートも取らずに机に突っ伏す。
「授業料払ってるのは自分だし、どう過ごそうと自由でしょ」という態度。
そして、教員に対しては適当にふるまい、企業の面接では猫をかぶる。
このような“相手によって態度を変える”人は、社会では信頼されません。



誰に対しても、同じように敬意を持てる人が信頼される。
それは上下関係ではなく、“人と関わる姿勢”の問題なんです。
社会では、たとえ相手が年下や立場が下の人であっても、態度が見られています。
その“素の部分”が評価を左右する時代です。
意外とすぐ気付かれるものですよ。
大学生活で身につけたい“当たり前”の5つの習慣


では、何を意識すれば“信頼される人”に近づけるのでしょうか?
難しいスキルではなく、今すぐできる小さな習慣が鍵になります。
①提出物に心を込める
ただ出せば良い、という姿勢はすぐに伝わります。
誤字脱字が目立つ、名前が書いていない、ファイル名が適当。
どれも「この人、ちゃんとしてないな」と感じさせてしまいます。



書いてある内容がいくら良くても、“雑さ”が先に見えてしまうと、本当に伝えたいことが入ってこないんです。
社会に出れば、資料や報告書、メール1通に至るまで「自分の顔」として見られます。
小さなことこそ丁寧に仕上げる習慣が、信頼の第一歩です。
これだけで「ちゃんとしている人」という印象を持ってもらえます。
1つ1つの提出物は、実はよくみられています。


②メールを正しく書く
メールは“言葉の身だしなみ”です。
「件名なし」
「挨拶なし」
「いきなり本文だけ」
「署名がない」
こうしたメールは、それだけで「配慮が足りない」「子どもっぽい」と見なされてしまいます。



“こういうとき何て書いたらいいか分からない”って言う人、けっこういます。分からないなら、調べる。調べても不安なら、誰かに聞く。それも社会に出るための練習なんです。
基本の型さえ身につければ、メールは怖くありません。
就活・バイト・ゼミ・社会人とのやり取り、どの場面でも役立ちます。
メールの書き方一つで、あなたの人柄と誠意が伝わります。
③挨拶と礼儀を大切にする
「おはようございます」
「ありがとうございます」
それだけで空気が明るくなります。
逆に、挨拶もせずにスッと教室に入って、黙って座る…。
そんな姿を見て、「この人と一緒に働きたい」と思えるでしょうか?
礼儀は、相手への“リスペクトの表現”です。
言葉づかいや立ち居振る舞いも、意外と見られています。



“礼儀正しい”っていうのは、ルールを守るとか型にハマるって意味じゃなくて、“相手を不快にさせない配慮ができるか”だと思っています。
④整理整頓を習慣にする
部屋や机の状態は、心の状態とつながっています。
レポートの締切を忘れる人の机は、たいてい散らかっているし、
準備不足の人のカバンは、必要なものがすぐに出てこなかったりします。
整理整頓ができる人は、時間や情報の管理もうまい。
社会では「仕事ができる人」として見られやすくなります。



自分の空間が整うと、頭の中も整うんです。1日5分、カバンの中を整理するだけでも変わりますよ。
提出物・スケジュール・持ち物などの整理は、自己管理能力を育てます。
⑤時間と約束を守る
待ち合わせに遅れない、締切を守る、事前に連絡を入れる。
これは信頼関係を築くうえでの“土台”です。
「ちょっとぐらい遅れてもバレない」
「誰も怒らないし、あとで出せばいい」
そう思っている人は、いつか大切なチャンスを逃します。
社会では「時間を守れる=信頼できる人」と見なされます。



“ちゃんとやってくれる人”って、それだけで貴重なんです。時間を守るって、地味だけど最強の信頼貯金です。
これだけで「信頼できる人」の土台ができあがります。
自由と責任のバランスを考える


大学生は「大人として扱われるけど、まだ未熟な部分もある」という、非常にグラデーションのある時期です。
その中で手にする“自由”は、あなた自身の判断で動ける力を育てるために与えられています。
でも、「自由=好きなようにやっていいこと」だと勘違いしてしまうと、
気づいたときには「信頼されない人」になってしまっていることもあります。
自由な時間、自由な選択、自由な行動。
そのすべてには、本来“責任”が伴います。



例えば、授業に出るか出ないかを決めるのは自由。でもその結果が“単位を落とす”という責任として返ってくるんです。
自由が多くなるほど、自分の選択が未来に与える影響も大きくなります。
そしてその選択の積み重ねこそが、“信頼”や“評価”としてあなたに返ってくるのです。
だからこそ、大学生活の中で「責任ある自由」の感覚を身につけることはとても大切です。



自由の裏には、必ず責任がある。この感覚を持てるかどうかで、社会に出た後の過ごし方は大きく変わります。
このあたりについては、次回記事でさらに詳しくお話ししていきます。
👉 自由の裏には責任があるという話(近日公開予定)
まとめ|信頼される人になるために、今できること


大学生活は、自由でのびのびと過ごせる時間かもしれません。
でも本当は、「社会に出る準備をするためのステージ」です。
自分で考えて行動する力、責任を持って選択する力、そして他者と信頼関係を築く力——
そうした力を育てる絶好の機会なのです。
私が大学教員として日々学生と接する中で感じているのは、
「社会に出られない学生」には、共通する特徴があるということ。
それは知識や能力の不足ではなく、
提出物の雑さ、メールや言葉遣いの乱れ、態度の軽さ、そして責任感のなさといった“姿勢の部分”です。
しかし、逆に言えば——
小さな「当たり前」を大切にすることで、人は驚くほど信頼されるようになるのです。
- 丁寧な提出物
- 正しいメールの書き方
- 礼儀ある立ち居振る舞い
- 整った生活習慣
- 時間と約束を守る責任感
どれも今すぐに意識できることばかりです。
そしてそれが、将来のあなたを支える土台になっていきます。



自由は“何をしても許される”ことじゃない。“自分で責任を持って選ぶ”こと。そういう力を、大学生活の中で育てていってほしいんです。
「社会に出るのが不安」
「自分に自信がない」
そう思うなら、まずは今日から、“当たり前”を丁寧にやってみませんか?
みんなで笑顔になる暮らしの第一歩を、ここから踏み出していきましょう。









